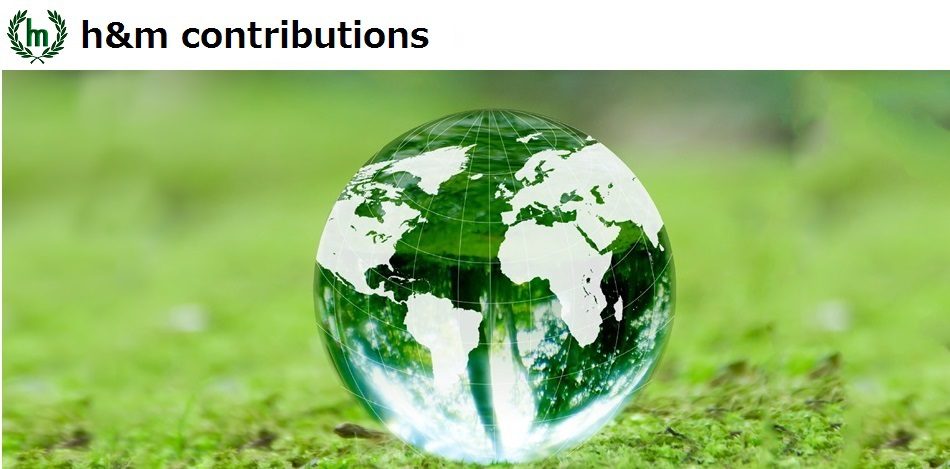手軽な夏疲れ解消法
手軽で効果的な夏疲れ解消法
空の青さが夏らしく輝きを増してきた今日この頃、夏本番に向けて体調管理を心掛けたい時時季ですね。
たまった疲れは年々取れにくくなり、体調を崩す原因にもなります。
そこで実践したいのが、毎日簡単に続けられる疲労解消法。
日々の生活に上手に取り入れて、身体の芯から元気を取り戻しましょう。
<生活習慣に取り入れやすい「夏疲れ対策」>
夏特有の疲労感や身体のだるさは、実は冷えが原因の一つであるともいわれています。
暑い夏はクーラーの利いた部屋で過ごすことも増えますが、人間の体温調整をつかさどる自律神経は、5℃以上の急激な気温変化に対処できず、バランスを崩してしまいます。
クーラーを使用する際は、温度設定に注意して、直接風があたらないように上着をはおるなどの工夫をしましょう。
もし不調が出てしまった場合は、自律神経を高め、血行の流れを促進してくれる適度な運動がお勧めです。
涼しい夕方からのウォーキングや、深い呼吸に合わせて全身の血流をよくするヨガのポーズなど、日課として取り入れてみてはいかがでしょう。
<エネルギーを生み出す仕組みを知ろう>
夏疲れ対策には、エネルギーを生み出す仕組みを知ることも大切です。
私たちが生きていくために必要なエネルギーの供給は、日々の食事から始まります。
食べ物によって得られた栄養素は体内で分解され、その代謝活動の過程で、私たちが日々日々活動するために必要なエネルギーが生み出されています。
これは「クエン酸回路」と呼ばれ、人間の生命活動を支える重要な働きをしています。
クエン酸はこれらのエネルギーサイクルを活性化させる役割がありますので、クエン酸を摂取するのも疲れ解消の一つの方法です。
<食生活に取り入れたい「夏疲れ解消法」>
これからの暑い時季には、やはりさっぱりとしたものが食べたくなるものです。
そんな時には食が進みやすくなる酸っぱい食材がお勧めです。
レモン、グレープフルーツ、オレンジなどの柑橘類や、他にもイチゴ、パイナップル、キウイには、クエン酸やビタミンCなど疲労解消に効く成分が含まれています。
すっきりした後味は減退した食欲をかきたててくれる役割も。
夏バテ対策には備えておきたい食材です。
これから暑さも本番となってきますが、適度な運動を取り入れた生活習慣と、食生活を意識して夏を乗り切りましょう。
化粧品はデリケート
化粧品を最後まで気持ちよく使うために!
化粧品はデリケート。
雑菌や酸化のせいで品質が劣化した化粧品を使い続けることが、お肌のトラブルの原因になることもあります。
化粧品を使うときは扱い方や保存方法に気を付けて、開封後はなるべく3か月~6か月以内に使い切りましょう。
◇容器のフタやキャップはしっかり閉めましょう。
化粧品は空気に触れることで酸化したり、空気中の雑菌が入ったりすることがあります。そのため、使用前はしっかりと密封された状態になっています。
封を開けて使い始めた後も、キャップを開けたままや、隙間がある状態にしておくと品質の劣化や、菌の繁殖が早まってしまいます。
できるだけ早くキャップをしっかりと閉め、長い間空気にさらすことのないようにしましょう。
◇冷暗所に保管しましょう。
高温・多湿や直射日光が当たる場所に保管していた化粧品は、食品と同じで劣化が早くなってしまいます。
化粧品は、日光があたる場所やお風呂場、脱衣所など湿度が高くなりやすい場所を避け、なるべく涼しい場所に保管しましょう。
とはいえ、化粧品は急激な温度変化を嫌うので、冷蔵庫での保管はお勧めできません。また、冷やして使うことで、使用感が良くないと感じることもあるようです。
◇多く取りすぎたからといって容器に戻さないようにしましょう。
化粧品は手の雑菌が入ることで品質が劣化しやすくなります。
一度手に取った化粧品には手の菌が付いてしまっているので、容器に戻すと雑菌が繁殖してしまいます。
クリームに限らず、美容液、シャンプー、トリートメントなども、ったいなくても使い切るか捨てるようにしましょう。
クリームは面倒でも指をそのまま入れるのではなく、スパチュラを使用して、使用後はきれいなティッシュなどでクリームを拭き取ってください。
また、容器の口に中身が付いている場合もこまめに拭き取りましょう。
<化粧品を上手に保管するコツ>
①容器のフタやキャップはしっかりと閉めて参加を防止する
②高温・多湿・茶クシャ日光の当たる場所で保管しない
③指で直接取り出したり、容器に戻したりしない
実は化粧品には消費期限があるのをご存知ですか?
正しいスキンケアで快適なビューティフルライフを!
ストレスが多くなる季節
<ストレスが多くなる季節です>
新年度を迎えて 入学や就職、異動、一人暮らしなど新しい環境への期待があり、やる気があるものの、その環境に適応できないでいるという方も多いのでは?
変化の多いこの時期は、 一年の中でストレスがたまりやすい季節だといわれています。
ご自身はもちろんですが、ご家族やお知り合いの中にも「最近、表情が浮かないな…」という方はいませんか?
<「変化」に疲れていませんか?>
新年度を迎えて生活の中では様々な「変化」が起こります。
会社や学校の中ではもちろん、朝晩の寒暖差、花粉症など、環境の変化も大きい季節です。
私たちにとって「変化」は、たとえ良いことや些細なことであっても「ストレス」になります。
そして知らず知らずのうちに蓄積されていき、心に負担を掛けてしまいます。
最近、身の回りでどんな「変化」がありましたか?
いつもよりストレスがたまっていませんか?
<ストレスがたまってしまうと…>
人によって差はありますが、私たちにはストレスを抱えられる許容範囲があります。
その限界を超えてしまうと、からだに様々な症状が現れてしまうのです。
例えば、食欲不振、吐き気、動悸、不眠、気分の落ち込み、意識低下…
一度そのような状況に陥ってしまうと、回復までに時間がかかりますし、場合によっては、自力での回復が難しくなり、病院での治療が必要になります。
「まだ大丈夫」と無理をせず、1日事にストレスを発散し、明日に向けて新しい活力をチャージしていくことが大切です。
<ストレスは小まめに解消しましょう>
ストレスがたまると、視野が狭くなり、正しい対応や判断ができなくなります。
さらに自分を追い込んでしまったり、マイナス思考の悪循環に陥ったりしてしまいます。
「自分は今、ストレスを感じているな。良くないな。」と思う余裕がある間に解消しましょう。
ストレス解消法としては「趣味に没頭する」「運動で汗を流す」「リラックスしてゆったり過ごす」などがあります。
<自分にあったストレス解消法をみつけましょう>
自分に合わないストレス解消法では意味がありません。
「運動で汗を流す」のが良いからといって、苦手な人には逆効果になることも。
日頃から自分に合ったストレス解消法をいくつか見つけておきましょう。
バランスのとれた食事や、良質な睡眠は、何より心の栄養になります。