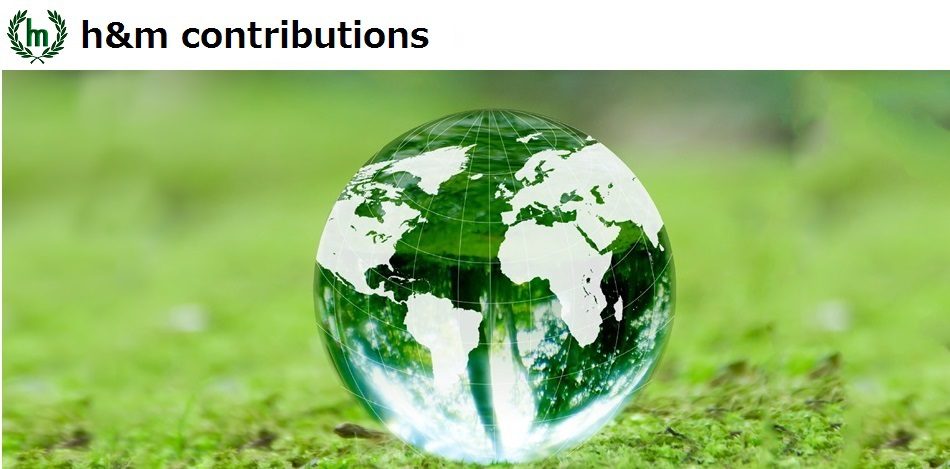高齢化の現状と将来像

我が国の総人口は、2016年10月1日現在、1億2,693万人となりました。65歳以上の高齢者人口は、3,459万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)は27.3%となっています。
この高齢化が加速する状況の中で「2025年問題」という言葉が取りざたされています。
「2025年問題」とは、団塊の世代が2025年頃までに後期高齢者(75歳以上)に達する事により、介護・医療費等社会保障費の急増が懸念される問題です。
高齢者人口は、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年には3,657万人に達すると見込まれています。
介護や福祉分野の需要はますます増え、医療費などの社会保障費が急膨張する中、医療・介護のサービス体制の抜本的な見直しが必要とされています。
その後も高齢者人口は増加を続け、2042年に3,878万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計されています。
総人口が減少する中で高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、2035年に33.4%で3人に1人が高齢者となります。
2042年以降は高齢者人口が減少に転じても、65歳到達者数が出生数を上回ることから高齢化率は上昇を続け、2060年には39.9%に達して、国民の約2.5人に1人が65歳以上の高齢者となる社会が到来すると推計されています。
これまでの高齢化の問題は、高齢化の進展の「速さ」の問題でしたが、2015年以降は、高齢化率の「高さ」(高齢者数の多さ)が問題となります。
高齢者(65歳以上)1人に対して生産年齢人口(15~64歳)が何人で負担するか?という社会保障費用も、今までの「胴上げ型」から現在は「騎馬戦型」、そして2050年は「肩車型」社会へと大きく変化していきます。
「1965年/胴上げ型」高齢者1人に対し生産年齢人口9.1人
「2012年/騎馬戦型」高齢者1人に対し生産年齢人口2.4人
「2050年/肩車型」高齢者1人に対し生産年齢人口1.0人
低い出生率と、諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行し、年金等厳しい社会保障費負担の社会の到来が予想されます。
誰しも考える老後の生活についてですが、こんな生活を送りたい!と具体的考えたことはありますか。
その理想の老後の生活を送るためには、何が必要となりますか。
健康な身体、長く続けられる趣味、そして経済…
60歳で定年を迎えて年金受給が始まるまでの5年間夫婦二人の年間の生活費は?
仮に年間300万円とすると5年間で1500万!
それだけの蓄えをしておくか、60歳を超えても安定した収入源を持っているか。
そして自分自身の年金受給額はいくらなのか。
平均寿命が90歳を超えると言われている今、老後の生活設計はとても重要で避けては通れない問題です。
今後は、老後も何らかの形で収入を得続けることが重要になります。
会社員として定年まで勤めた後、のんびり生活するスタイルを変えなければいけないのです。
そして、こうした状況で重要になってくるのが「①現役時代に力をつけておくこと」「②稼げる副業や、稼げる仕事を見つけること」なのです。老後の自立を確立して、安心して老後を過ごすために、今からどんなことが準備できるのでしょうか。
できれば早いうちから準備を始めて、老後は豊かにのんびりと過ごしたいものです。