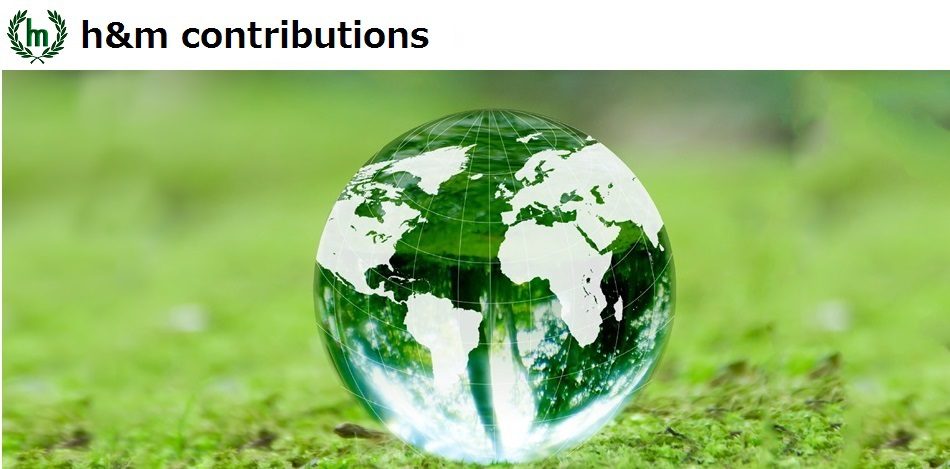最近よく聞く老後破産

最近「老後破産」という言葉を頻繁に、目に耳にするようになりました。
そこには誰もが認識している時代の背景があります。
少子高齢化が進む中で、年金の給付水準を引き下げざるを得ない一方、医療や介護の負担は重くなっています。ひと昔前の世代では60歳で定年退職を迎え、定年後は自宅で「毎日が日曜日」という暮らしを送る例も多くありました。しかし、その世代と現在50歳代以下の世代では決定的に違うことがあります。
それは、当時の年金支給が60歳からだったということです。
現在、年金は65歳支給への移行が着々と進められており、男性の場合、昭和36年(1961年)4月2日以降生まれの人は、年金の支給開始が65歳からになります。つまり、60歳で定年退職すると65歳までのまる5年もの間、原則年金ゼロ(無収入)という深刻な状況になってしまうのです。
以前の日本は、定年(引退)のない自営業者が多かったのですが、高度経済成長以降、会社員という働き方が増えていき、定年で引退という概念が考えられるようになったのです。
<そもそも老後破産とは?>
老後破産とは、定年退職後(または自営業者のリタイア後)の高齢者の経済状態が貧困状態になってしまうことです。
「生活保護水準以下の収入しかないにもかかわらず、保護を受けていない」破産状態にある高齢者の現状を「老後破産」と呼びます。
<老後破産に陥ると、どうなる?>
取り崩せる貯蓄や収入もなく、年金のみの生活になるため、経済的に苦しい状況に置かれます。年金だけでギリギリの生活ができていたとしても、高齢になると病気や介護といったリスクも高くなるため、想定外の病気になる可能性もあります。
しかし、そんな時に治療費が支払えず、病院に行くことを躊躇する事態も考えられます。
現役世代には頑張って働いてきたのに、「こんなみじめな老後を過ごすことになるとは」という気持ちになり、長生きそのものに不幸を感じる人も少なくありません。
■老後の四大破産■
① 住宅ローン破産
② 老人ホーム破産
③ 医療費破産
④ 介護破産
<老後破産が増加している理由>
生活に困窮している人の中に高齢者が含まれていること自体は昔からあったはずですが、なぜ今になってここまで問題視されているのでしょうか。
それは老後破産になる人が急増しているためで、そこには以下のような理由が考えられます。
• 終身雇用が事実上なくなり生涯年収が減少する人が増加した
• 年金受給開始年齢が引き上げられた
• 長寿の人が増え老後の必要資金が増加した
• 晩婚化で子供を設ける年齢が高くなった
• 定年後に浪費をする人が多くなった
• 景気低迷によって貯蓄額が減った
この他にもさまざまな理由が考えられますが、今までの雇用システムや給与体系等、収入の仕組みそのものが変化したことによって、人生設計の考え方にも、これまでの常識が通用しなくなりつつあることを示しています。
<まとめ>今後は、老後も何らかの形で収入を得続けることが重要になります。
会社員として定年まで勤めた後、のんびり生活するスタイルを変えなければいけないのです。
そして、こうした状況で重要になってくるのが「①現役時代に力をつけておくこと」「②稼げる副業や、稼げる仕事を見つけること」なのです。老後の自立を確立して、安心して老後を過ごすために、今からどんなことが準備できるのでしょうか。
できれば早いうちから準備を始めて、老後は豊かにのんびりと過ごしたいものです。